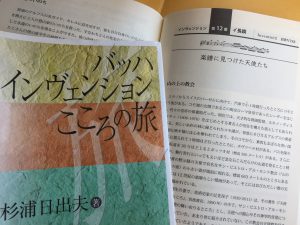教則本は「うたとピアノの絵本」
楽譜の音域に合わせると真ん中が「ド」で、そこにおへそがくるように座ってもらいます。
右手はド・レ・ミにおいて、左手をド・シ・ラの位置におきます。
この教本のよいところは、字が大きくて見やすいことや、ト音・ヘ音記号を導入から取り入れていけるので、小さいお子さまでも自然にヘ音記号が読めることです。

自分で指の番号を書いてシールをはったら、次に伴奏に合わせて歌ったり、リズムを打ったりします。
指導のとき大事にしているのは「ちょっとだけ、手ごたえを感じて帰る!」ことです。
メロディーを口ずさみたくなるころには、もう弾けています。